ポイントは背表紙を揃えること!簡単にできる本棚の整理方法

本好きの人に多いのが「いつの間にか本があふれかえっている」という悩み。一度散らかってしまうと、どこから手を付けていいのかわからず、悩んでしまいますよね。
そこでこの記事では、片付けが苦手な人でもすぐに取り組める本棚整理のテクニックを紹介します。文庫本や漫画など、特定の本が多い人のために、本の種類ごとの収納方法も紹介しているため、ぜひチェックしてください。
簡単にできる本棚整理の4ステップ
美しい本棚を作るためには、整理整頓がしやすい本棚をつくることが大切です。まずは、片付けが苦手な人でも簡単にできる本棚の整理方法を4ステップに分けて解説します。
1. 本を出す
本棚を整理するためには、「読まない本を減らす」「本を種類別に分ける」ことが重要です。そのためには、まずは家中にある本を一度全て1カ所にまとめてしまいましょう。
本をすべて出すことによって、現在所有している本の量を視覚的に理解することができます。こうすることで、本棚のサイズは適切か、何冊程度減らす必要があるのかなどを予測することができます。
このとき、あきらかに処分してもよさそうな古い雑誌などは、すぐに処分できるように先によけておきましょう。
2. 本を分類する
次に、出した本を分類していきます。
なお、本の数が多い場合は、あらかじめ大きめの段ボール箱やバスケットなどを用意しておきましょう。本の整理を中断しなくてはならなくなってしまっても、一旦箱に収納しておけば、部屋を散らかさずにまたすぐに再開することができます。
>>ニトリ「カラボサイズふた付きボックス」
本を1冊ずつ確認しながら、読む頻度に合わせて分類していきましょう。
ただし、分類をするときは本の中身を読んではいけません。全ての本に目を通していたら本棚の整理が終わらなくなってしまいます。チェックは表紙と目次までにして、本文は読まない様に注意しましょう。読んだはずなのに内容が思い出せないような本は「もう読まない本・処分する本」に分類して構いません。
分類する基準の一例は以下の通りです。
よく読む本・手元に置いておきたい本
日常的に読む本や、よく読み返す本は「よく読む本」に分類します。頻繁に読み返すことはないものの、愛着があって捨てられない本は「手元に置いておきたい本」です。金額ではなく、自分にとって大切がどうかで分類することがポイントです。
いつか読むかもしれない本
残すか捨てるか決められない本は、「いつか読むかもしれない本」に分類しておきましょう。グレーゾーンの一時保管場所を確保しておくことで、1冊の本に悩む時間を減らし、整理を効率よく進めることができます。
読まない本・処分する本
自分自身で「もう読まないな」と感じる本はもちろん、古い雑誌や発行年月日が古い参考書・ビジネス書なども読まない本に分類します。参考書やビジネス書は情報を扱っているため、古くなると役立ちません。社会情勢や法律、ルールが変わっていることもあるため、勉強は最新版の本を買いなおして行いましょう。
未読の本
まだ手を付けていない未読の本は、1カ所にまとめておくことで読み忘れを防げます。本棚の中に未読の本コーナーを作り、本が溜まらないように心がけましょう。
3. 本をジャンル分けする
本を分類したら、次は本棚に収納するための下準備です。使いやすい本棚を作るためには、図書館の様にジャンルごとに分けていきましょう。漫画、文庫本、雑誌‥‥と分けたら、続いてホラー、エッセイ、グルメなど自分の本に合ったジャンル分けをしていきます。
ジャンル分けと同時進行で進めたい作業が「インデックス作り」です。本を本棚に戻すときに、そのまま並べてしまってはジャンル分けした意味がなくなてしまいます。厚紙や空のCDケースなどを活用し、見やすいインデックスを作りましょう。
統一感のあるインデックスを作りたいときは、パソコンやスマートフォンで作れるラベルシールがおすすめです。
>>ブラザー販売(株)「スマホで使えるラベルライター P-TOUCH CUBE」
4. 本棚に収納する
最後に、「よく読む本」「手元に置いておきたい本」「未読の本」を本棚に収納していきます。本棚に本を並べる時には、背表紙の高さと面を揃えることを意識しましょう。背表紙の面は、手前にそろえます。収納するときには本を奥に詰めこみがちですが、背表紙の面を手前に揃えることで美しく見せることができます。
「いつか読むかもしれない本」は、本棚に置くと収納スペースを圧迫するため、箱に入れて押入などに収納しましょう。「読まない本・処分する本」は捨てたりフリマアプリで売却したりして処分してください。
【ジャンル別】収納のポイント
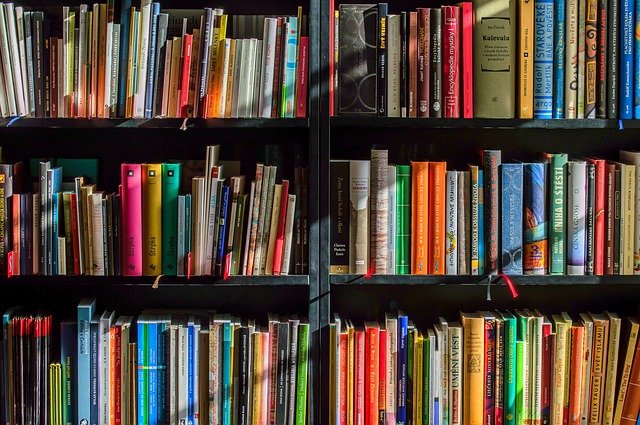
ここからは、本のジャンル別に収納のポイントを紹介します。本棚がコンパクトな人や、本棚の使い勝手が悪い人はぜひチェックしてください。
文庫本
文庫本はサイズが小さいため、一般的な本棚では奥行きがあまりがち。本棚に文庫本をより多く収納するためには、2列にして収納しましょう。奥に収納された文庫本も、ティッシュボックスなどで作った踏み台を活用すれば、背表紙が見えるようになります。
漫画
漫画は、人気作ほど一作品当たりの巻数が膨大になりがちです。そのため、奥行きや拡張性のある収納力の高い本棚がおすすめです。
>>ワイエムワールド「ダブルスライド書棚奥深タイプ」
または、全てのマンガを本棚に収納するのではなく、1巻ごとに「よく読み返すエピソードなのか?」と考え、最新刊やお気に入りの巻だけ本棚に収納するという方法もあります。本棚に収納しない漫画は、漫画専用の収納ボックスに入れて押入れやクローゼットなどに収納しましょう。
>>アイリスプラザ「コミック本ストッカー」
雑誌・パンフレット
雑誌やパンフレットは、必要なページのみ切り取って保存しましょう。
スクラップブックに貼り付けたり、100円ショップなどで購入できる書類ケースなどに収納すれば、コンパクトにまとめられます。
大型本
本棚から飛び出してしまう大型本は本棚ではなく、カラーボックスやシンプルなラックに収納しましょう。大きさやデザインにバラつきがある大型本は、おしゃれな箱やバスケットとに入れてから収納することで、本棚を美しく見せることができます。
>>ニトリ「バスケット ライラ3」
本棚のデザインやインテリアによっては、一部の大型本を表紙が見えるように置き、「見せる収納」化するのもおすすめです。
入りきらない本や普段読まない本は収納サービスを活用する

本棚を美しく保つためには、本棚に収納する本の量を本棚の7~8割程度になるように調整しましょう。本棚に入りきらない本は専用ボックスなどに入れ、押入れやクローゼットなどに入れるといいでしょう。
押入れやクローゼットもいっぱいで、 収納場所に困っている人には、「カラエト(CARAETO)」がおすすめです。
「カラエト」は、月額240円から利用できる宅配型収納サービスです。「カラエト」では、段ボール箱に本を詰めて送るだけでセキュリティ対策が徹底された専用倉庫に保管することができます。
専用倉庫では空調も管理されているため、貴重な本をカビやほこりから守りながら保管が可能。さらに預けた本はアプリでチェックできるので、どの本を預けたのかも一目瞭然です。
本の整理や収納になたんだときは、ぜひ「カラエト」を利用してみてくださいね。








