自分で遺品整理をするコツ!メリット&デメリットは?

大切な人を亡くしたあとは気分が沈み、遺品整理も進まないものです。
とはいえ、故人が借家に住んでいた場合などは遺品整理のタイムリミットもあります。間に合わない場合は整理されていない荷物を引き取ることになったり、大切な遺品を間違って処分してしまうことも。
遺品整理は効率よく進めることが大切です。この記事では、自分で遺品整理を効率よく進めるための方法を紹介します。
また、どうしても遺品整理が終わらないときに便利なサービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
自分で遺品整理をするメリット・デメリット
遺品整理は自分で行う以外に、遺品整理の専門業者に頼む方法もあります。悲しい時期に自ら遺品整理を行うメリットは何があるのでしょうか。
メリットとデメリットを両方確認し、後悔のない遺品整理を行いましょう。
メリット
まずは、メリットを解説します。
〇心の整理がつけられる
遺品をひとつひとつ自分の目で確かめたり、故人との思い出を思い返したりしながら整理をすることで、心の整理がつけられます。
〇費用を抑えられる
遺品整理の専門業者に依頼した場合、部屋の広さにもよりますが10~20万円ほどかかります。
自分で遺品整理した場合は、かかる費用はゴミ袋や家電の処分費用程度です。人件費やトラック代がかからないため、比較的費用を抑えて遺品整理が可能です。
〇トラブルに合うリスクが少ない
業者などの第三者を介入した場合、「捨てる予定じゃなかった遺品を捨てられた」「遺品を破損させた」などのトラブルに合うリスクがあります。
自分で遺品整理をしていれば親族で話し合いをしながら遺品整理を進められるため、トラブルに合うリスクが少なくなります。
デメリット
続いて、デメリットを解説します。
〇遺品の処分に手間がかかる
人が生活していた空間には、想像以上にたくさんのものがあります。
食品や衣類などを捨てるだけでも、ゴミ捨て場と住居を何往復もしなければならないでしょう。
また、遺品整理で処分するものは、日用品や衣類、雑貨だけではありません。家具や家電など大型のものもあり、単に「処分する」といっても簡単ではありません。中にはパソコンやエアコン、テレビなど特殊な方法で処分する必要がある家電もあります。
遺品整理には体力が必要です。協力してくれる人の人数はできるだけ多い方が良いでしょう。
〇時間がかかる
当然ながら、遺品整理のプロである専門業者が作業するよりも時間がかかります。見つけたアルバムを読みふけってしまったり、一緒に遺品整理をする親族と話し込んでしまったりすることもあるでしょう。
ゆっくりと心の整理ができる反面、多くの時間が必要になります。
遺品整理を効率よく進めるための5つのステップとコツ
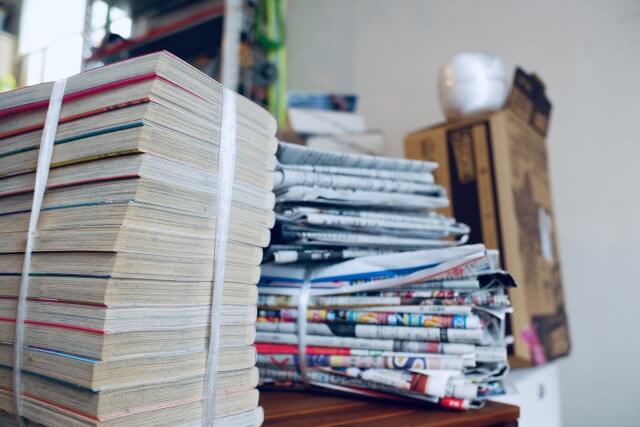
ここからは、遺品整理を進める5つのステップを紹介します。
1.スケジュール調整をする
まずは、できるだけ早くスケジュール調整をしましょう。粗大ごみの処分など、不用品の処分には日数がかかります。故人が賃貸で暮らしていた場合、退去の手続きも必要になります。遺品整理が長引いてしまうと、住人のいない家に家賃を支払うことになってしまいます。
また、遺品整理はなるべく親族が集まれる日に行いましょう。誰かが遺言状をもっている可能性があります。また、思わぬ貴重品や財産が見つかった場合に備えて実際に遺品整理を行う人だけではなく、遺産相続の話をまとめる人も同席していることがベターです。
遺品整理は人手が多い方がトラブルも少なく、作業もスムーズに進めることができますよ。
〇決めたい項目
- 何日から何日に遺品整理を行うか
- 参加者は誰か(鍵の管理者は誰か)
- 何日にどこの部屋を片付けるのか
2.貴重品や書類を集める
遺品整理当日は、遺品の仕分けから始めます。
端から整理していきたいところですが、まずは部屋の中から貴重品や重要な書類を集めましょう。大抵の場合、貴重品や重要な書類は一カ所にまとめられてあるため、紛失しないように他の遺品とは分けて管理します。
〇貴重品や重要な書類の例
- 預金通帳
- 銀行口座やネットバンキングのパスワードなどが書かれたメモ
- 印鑑
- 自宅の鍵
- 現金・財布
- 有価証券
- 電気・ガスなどの契約書類
- その他各種契約書
- 写真・アルバム
3.遺品を分類する
いよいよ遺品の整理を始めます。
まずは遺品を「残す遺品」「処分する遺品」「検討中」「高価な遺品」に分類していきましょう。特に、貴金属などの高価な遺品は相続税の課税対象となることがあるため注意して分類します。
課税対象とならなくても形見分けの際にトラブルになることもあるため、あらかじめ分類しておき、親族で相談してから整理した方が良いでしょう。
4.不要な遺品を処分する
「処分する遺品」に分類したものを処分します。処分方法は主に2つあり、売却するか捨てるかです。
〇売却する
まだ使える家電や家具、書籍などは、フリマアプリやネットオークション、リサイクルショップなどを活用して売却するのがおすすめです。
なお、貴金属や骨董品など自分で価値が判断できないものは「鑑定士」のいる業者に買い取ってもらいましょう。オークションサイトなどでは知らないうちに安価で取引成立してしまう可能性があります。
ただし、遺品の売却金額が高額になった場合には相続税の対象となるケースもあります。大量に出品したり、高額で売れた場合は、課税対象になるか必ず確認してください。
〇捨てる
小さいゴミは普段のごみと一緒に、大きいゴミはまとめて粗大ごみで処分します。エアコンなど一部の家電はリサイクル法にのっとって処分する必要があるため注意が必要です。
また、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを捨てるときは、個人情報が漏洩しないようにデータを消去してから捨てましょう。
5.遺品を分ける
「残す遺品」に分類した遺品を分けていきましょう。
遺品整理の中でも、形見分けは親族間トラブルが発生しやすい工程です。できるだけ多くの親族に声をかけ、トラブルのないように進めましょう。必要があれば遺品整理から日を改めて行うこともおすすめです。
遺品の整理や処分が終わったら、あとは部屋の掃除をして終了です。
故人の状態によっては「特殊清掃」という専門業者による清掃が必要になる場合もあります。
どうしても遺品整理が終わらない!そんな時に使えるサービス

最後に「自分で遺品整理を始めたけど全然終わらない!」と言うときに使えるサービスを紹介します。
遺品整理業者・リサイクルショップ
遺品整理業者やリサイクルショップに依頼すれば、遺品整理を一気に進めてくれます。全てを業者任せにするのが不安な人は「処分する遺品」の処分だけ依頼するのはいかがでしょうか。
遺品整理に慣れている業者であれば「実は金歯も売却できる場合がある」などのノウハウもあり、依頼者が損をしない工夫をしてくれますよ。また、大型家具など自分で処分するのが難しいものもまとめて片付けてくれます。
中には、ただ不用品を処分するだけではなく、お焚き上げなどの供養をしてくれる業者もいます。
収納サービス
「カラエト(CARAETO)」のような収納サービスを活用すれば「残す遺品」の整理に時間がかかってしまっても、部屋を空けることができます。住人がいない部屋に家賃を払いたくないときにはピッタリですね。
「カラエト」は、月額240円から利用できる宅配型収納サービスです。
預けたものを専用アプリでチェックできるので、実物を手元に置かなくても形見分けができます。大量の遺品を自宅に持ち込む必要もありません。また、専用マーケットがあり「預けたけれど、やっぱり要らないな」と思ったものをそのまま出品することができます。
「カラエト」を活用すれば、自宅の収納や生活スペースを圧迫せずに、ゆっくり遺品や心の整理ができますね。








